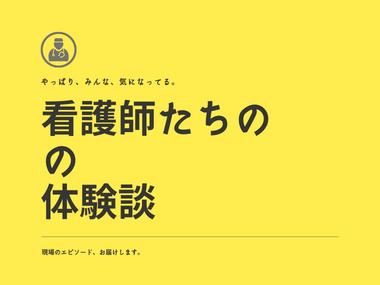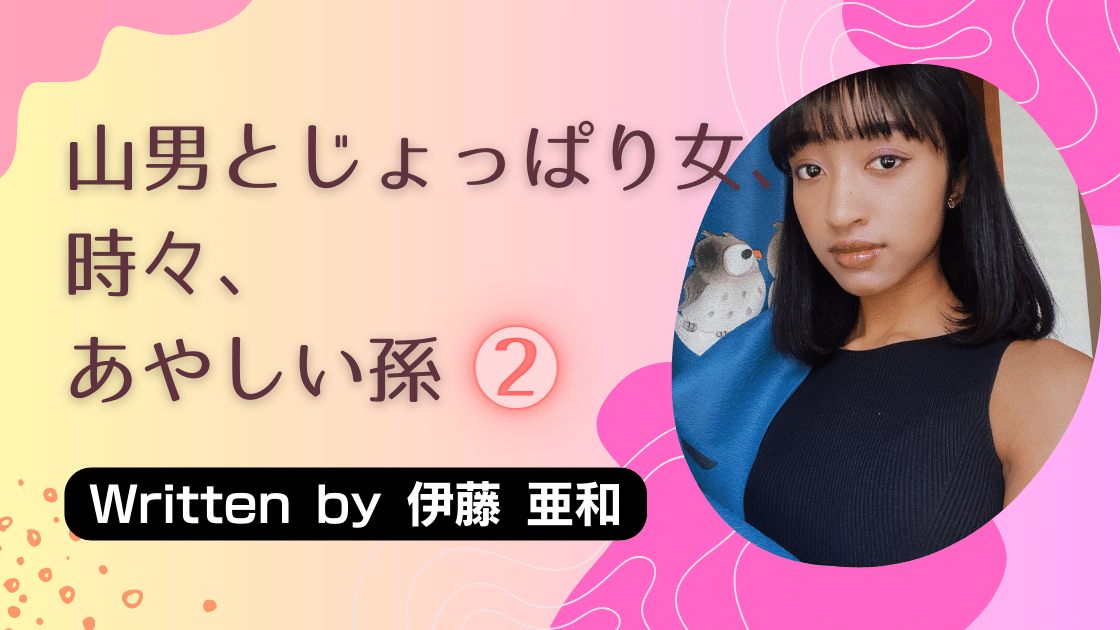
独特の感性と芸術性の高い文章力によりSNS等で話題の文筆家「伊藤亜和さん」によるオリジナルコラムです。
同居されている祖父母様との日常を甘辛な文章で紡いでいきます。
今回は祖父である「ジジ」と登山した時のお話。
それではどうぞ。
前回のお話はこちら
山男とじょっぱり女、ときどき、あやしい孫 ②

雲に触れたい。
なんてつまらない夢なんだろう。
私の場合、それは小学1年生の教科書に載っていた「くじらぐも」というお話を読んだときだったかもしれないし、ドラえもんの「雲かためガス」の登場回だったのかもしれない。
とにかく、人は誰もいちどは、雲に触ったり乗ったりできないものかと考える。

小学校高学年あたりの頃、ジジと富士山に登ることになった。
この頃はしょっちゅう一緒に山登りをしていたと思う。長野の天狗山から始まり、金時山、日向山、男体山、女体山だったかもしれない。それと丹沢のどっかの山と、なんとかって山と…たくさん登らされた。
私が今もめったに風邪をひかない丈夫な人間であるのは、この頃に付いた基礎体力のおかげなのかもしれない。
小さいながらに登山の楽しさが分かっていたかというと、べつにそういうわけでもなく、毎度茂みに待ち構える巨大な蜘蛛の巣や、木にビッチリと張り付くキクラゲの気色悪さ(食べるのは大好き!)に泣き叫びながらなんとか登頂する有り様だった。
私はただ根っからのジジっ子で、ジジが私を置いて朝早くから夜遅くまで山登りに行ってしまうのが我慢ならなかったのだ。
その挙句、富士山、ということになってしまった。
決行当日。
富士山の五合目まで、車で登るらしい。なんだ、五合目からスタートできるなんて楽勝じゃん。五合目まで行ったらあと五合しかないじゃん。
こんなにたくさん準備してきて損しちゃった。
とたんに肩の力が抜けて調子に乗った私は、山頂付近で摂取する予定だった「食べる酸素」なるタブレットを車の中でボリボリ食べ始めた。
「こらっ、食うな」
ジジが言う。だって美味しいんだもん。
グレープフルーツ味なのが悪い。
登山のメンバーは大体決まっていて、ジジの他に2人か3人、ジジの友達のおじいちゃんたちがいる。
顔も名前もいまいち区別がつかないので、私は心の中で「おじいちゃんズ」と呼んだ。
五合目までの車道はだだっ広くて、両脇にはタンポポかなにかがたくさん咲いていた。
タヌキが死んでいるのも見た。

五合目には、よく整備された綺麗な地面に、地上と変わらないような建物がポツポツと建っていて、想像していたような、山の中の鬱蒼とした雰囲気は微塵も感じられなかった。
日本一高い山の、危険な道や断崖絶壁を思い描いていたところに、人間が怪我をしないように、安心安全に作り直されたショッピングモールのような場所が現れたので、私はまたまた肩の力が抜けてしまった。
普段着みたいな格好の人もいて、重装備の自分が恥ずかしくなった。
このままこの辺りのレストランで醤油ラーメンを食べて帰りたいな、と思っていると、さっきまで晴れていた空が、突然ドス黒い雲に覆われ、尋常でない雨と雷が降ってきた。
そう、山の天気は変わりやすい。ここはやはり山なのだ。本来、人が気楽に来れるような場所ではない。
薄暗いホテルの入り口に避難した私たちの前で、視界を奪われるほど眩しい雷が炸裂する。
近くのおばさんが小さい悲鳴をあげる。
登山どころではない。
この世の終わりだ。
そう思っておじいちゃんズを見上げてみると、私の絶望に反して、おじいちゃんズは呑気な顔をしていた。
ジジが言った。
「なぁに。すぐ晴れるさ」
しばらくすると、本当に雨は止んだ。
止んじゃった。
止んでしまったら登らなきゃならない。
五合だけ、五合だけ、走って登って、すぐ降りてこよう。そんなことを自分に言い聞かせながら、登山口にたどり着いた。
また霧雨が降ってきて辺りが霞む。
いつの間にか綺麗なアスファルトの道路はもう跡形もなく、目の前には赤い土の、草もほとんど生えていないような殺風景の坂道が広がっていた。
知らない人に「頑張ってねー」と声をかけられ、少し得意になって登り始めた。
坂道は想像していたより緩やかで、はやく帰りたい私はおじいちゃんズを尻目に大股でどんどん進んだ。
霧のせいで周りの景色も全く見えないし、本当になんにもない。
一体なにが楽しいの…。
買ってもらったばかりの金剛杖は、小さい体には長いし重いし、なんて邪魔なものを買ってしまったんだろうと後悔した。
ちなみにこの後悔から1、2年後、私は懲りずに修学旅行で木刀を買っている。
あのどデカくて高い木刀を買ったのは、学年の中では私と、嫌われ者の小笠原くんだけだった。
今でも長い棒を見ると心が躍る。
今「金剛棒」と検索したら、サジェストには真っ先に「邪魔」と出てきた。
やはり邪魔。
遠くに見える小屋に向かって無心で歩いて、おそらく1時間足らずで六合目に到着した。思っていたよりもずっとはやく着いたので、これなら夕方には帰れるぞと嬉しくなった。
夏休みの自由研究も兼ねていたのでテキトーに辺りの写真を撮った。
空は少しずつ晴れて日が差し始めていたが、暑かった記憶は全くないので涼しかったのだと思う。
ガストのおもちゃコーナで、散々ねだって買ってもらえなかった声変わりヘリウムガスの代わりに、今のところ必要になりそうもない酸素ボンベをシューシュー吸ってみた。
当然、声は高くならないのだった。

七合目、八合目、と金剛杖に焼印をつけて貰いながら登っていく。山の斜面には、わずかながら草が生えていた。
ゴロゴロした無機質な砂利の上をネズミが走っていくのを見て、生物はどこにでもいるのだと少し感動した。
なぜか、登っていくにつれて無性にバナナが食べたくなった。
八合目に着く頃には日が傾き始めていて、私ははやく進まなければ頂上に着かないとジジたちを急かしたが、ジジが言うに、次は九合目ではなく八・五合目で、私たちはそこで朝まで仮眠をとるらしい。
私はなんだか勿体ぶられたようで、腹が立った。
八・五なんて考えた奴、きっと性格が悪いに違いない。
小笠原くんみたいな奴なんだろう。
辺りはどんどん暗くなって、やっと辿り着いた八・五合目には、登って来たたくさんの人、仮眠用の小屋、そして驚くべきことに、バナナが大量に積まれた「バナナ売り場」があった。
電球で照らされた鮮やかなバナナの山に登山者が虫のように押し寄せていた。やっぱりみんなバナナが食べたかったのか。
「ジジ、バナナ買って」
「高いから駄目」
買ってもらえなかった。
山小屋の仮眠所には人がひしめいていた。
シウマイ弁当の米のように詰め込まれた人たちが真っ暗な部屋の中でモゾモゾと蠢いている。
疲れ切った人間の匂い。ボソボソと話す低い声。部屋の閉塞感と、小屋を飛び出して今すぐ家に帰ることもできない不自由さで、私の心はどす黒く浮遊していた。
はやく帰りたい。
もう、最初からずっと、はやく帰りたいのだ。
ほとんど眠れないまま、ご来光の時間を目指して小屋を出た。

頂上を目指す長い列が、上へ上へと続いていく。
道も、今までの小さな石ころの集まりから、大きな岩の塊になって一歩ごとに体力を奪っていく。
ジジは高山病を起こして真っ青な顔をしながら、私の「食べる酸素」をボリボリと食べ、酸素ボンベをシューシュー吸っていた。
私のせいでいくらも残っていなくて、少しだけ申し訳なくなった。
人の背中を追いかけて、後ろから押されるようにひたすら登り、山頂にたどり着いたのがどの時点だったのか、はっきりとはわからなかった。
ただ、登っていく太陽を茫然と眺めたあの場所が山頂でなかったことは確かである。
周りの大人たちが「あぁ…」とお漏らしをしたような声を出していた。
顔の青いジジが山頂のさらに後ろのほうを指さして
「あそこが本当の頂上だよ。行くか?」
と聞いてきたが、もはやうんざりしていた私は
「はやく帰ろう」
とだけ答えた。
「やり切った」と言い切れる一歩手前で力尽きてしまう性格はこの頃からのようだ。
そのせいで「達成感」や「成功体験」なる言葉と縁が薄い。はっきりと形のあるなにかを掴めないのは宿命だろうか。
良くも悪くも、気づかないまま尊い時間は過ぎていく。もう少しなら行けばよかったのにと、大人になった私は思っているよ。
これから起こることにも、私は何度もそう思うだろう。
やっと帰れる、もう二度とくるもんか。私はほとんど転がるように山を降りていった。
あまりにも砂利を削りながら下っていくものだから、ジジは後ろから
「お前のせいで富士山が低くなるだろ」
と笑った。
顔色は少し良くなっていた。

五合目から車に乗って、富士山の麓を目指して降りていく。
窓から頂上のほうを見ると、真っ白い雲が山肌に添うように浮かんでいた。
私はきっと、雲に触れたのだ。
ペンネーム:伊藤亜和(いとうあわ)
プロフィール:モデル・文筆家
<了>
おすすめ記事