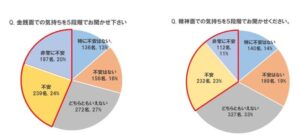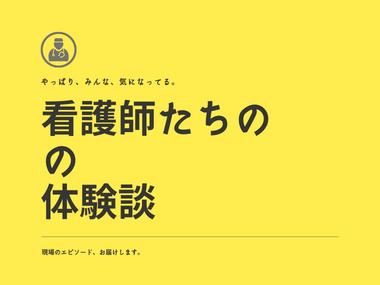独特の感性と芸術性の高い文章力によりSNS等で話題の文筆家「伊藤亜和さん」によるオリジナルコラムです。
同居されている祖父母様との日常を甘辛な文章で紡いでいきます。
今回は「サチの里帰り 前編」です。
それではどうぞ。
前回のお話はこちら
山男とじょっぱり女、ときどき、あやしい孫 ④

荷台には、大量の鳩サブレがみっちりと詰め込まれている。
コロナが始まってからの約3年間、祖母は生まれ故郷に戻ることができなかった。
私の友人のフォトグラファーは、コロナの真っただ中に青森を訪れて、宿の主人に「部屋は空いとらん」と追い返されてしまったらしい。そんなところに、例の豪華客船が来た横浜の人間がノコノコとやってきて、年寄りたちを訪ねまわるわけにもいかなかった。
コロナが終息するのが先か、それとも祖母の親戚たちが召されてしまうのが先か、私は勝手にやきもきしていたのだが、自宅隔離もなくなり、療養サポートサービスのLINEアカウントが消え、今やコロナは「普通にいる」ものとして受け入れられつつあった。
ギリギリまで「犬の世話が」とか「雪が危ない」とか言って足踏みをする祖母。
エッセイのネタとして、なんとしても青森に行きたい私。
そうしているうちに、長いあいだ世話をしていた親戚の犬が死んだ。
「これは『行っておいで』ということなのだろう」。
誰も口に出さなかったけれど、みんなそう感じていたと思う。犬の埋葬をして、祖母は翌日から支度を始めた。
車に荷物を詰め込んで、まっすぐな東北道をひたすら北上する。栃木の日光のあたりからぽつぽつと雨が降ってきて、福島に入るころには、正面から叩きつけられるような激しい雨が車のフロントガラスに向かって飛んでくるようになった。運転しながら聞こうと思っていたラジオの音も、雨の音のせいで何も聞こえなくなり、後部座席で退屈そうにしている祖母のために津軽の民謡を大音量で流した。
祖母は耳が遠い。
それは歳をとったからというわけではなく、若いころから難聴を患っているためだった。
祖母はよく、幼いころに米軍のダンプカーに轢かれて大けがをしたときの話をするが、それが難聴と関係しているのかはわからない。
近場に出かけるときは、運転席に祖父、助手席に祖母が座って、私が後部座席でスマホをいじっている、というのがお決まりのポジションなのだが、長距離を運転しなければならない今日は、私と祖父が数時間ごとに運転席と助手席を交代した。私が運転しているあいだは、ジジも後ろに座ってタチ(おばあちゃん)とお話してあげなよ、と提案もしてみたが、照れ屋な祖父は案の定「いやだね」と言う。前後の距離に加えて雨の音もあり、最初は声を張って続けていた会話も疲れて徐々に減っていき、弘前につく頃には車内の全員が沈黙していた。
沈みかけた日、寂れた町、ほとんど人もいない。
運転の疲れも相まって、私はハンドルを握りながらわけもなく涙が出そうになった。
なにもない。
都会と比べた不便さに涙が出そうになったわけではない。ただ、この町には切ない気持ちが似合うだろうと体が感知して、年寄りを連れたただの旅行が、まるでドラマティックな逃避行のように演出されたのだ。
もう戻れない…このままどこか遠くへ…と太宰治のように思いつめた顔で田んぼに囲まれた道を進む。
いつのまにか私たちは、冷たい風が吹きつける津軽海峡…ではなく、東横イン弘前駅前に到着していたのだった。
チェックインを済ませてから少し休憩をして、それから晩御飯にありつくためホテルを出た。せっかくなので津軽らしいものが食べたい、というのが3人の総意だったのだが、駅前には数件居酒屋があるだけで選択肢がそれほどない。スマホで調べてみると車で少し行ったところに津軽三味線の演奏が聴ける居酒屋があることがわかったので、私は運賃をしぶるふたりを「こういうときくらいいいじゃないか」と説得して、タクシーに乗り込んだ。
店に到着して祖母と私は生ビールを注文した。
下戸の祖父はこんなときでもコーラ。目の前の小さなスペースには2棹の津軽三味線が準備してあった。ホッケやゲソ揚げを注文して演奏が始まるのを待つ。
隣の席では青森がいかに良いところかという話題の津軽弁が聞こえた。みんな地元の人のようで、自分が住んでいる土地について日ごろからこうして語っているのを見るところ、本当に故郷を愛しているのだなと、思う。
横浜ではまず見ない光景だ。
ビールから日本酒に切り替えてうとうとし始めたころ、客席に座っていたおじさんがふいに立ち上がって三味線のほうに向かっていった。
おじさんがスペースに腰かけて三味線を弾き始める。おじさんは小気味良く2、3曲を弾いて、一番前に座っていた私に「意外と音が大きくてびっくりしたでしょ?」と得意げに言った。
私は笑顔をつくってニコニコと「そうですねぇ」と返事をした。
私は、10年ほど前から津軽三味線を習っている。
そのことは今日この場では口にしないでおこうと決めていた。伝統芸能の世界は複雑で、私が流派やなんやらをぺらぺらと喋って出しゃばったりしたら、師匠方に迷惑がかかるかもしれないからだ。大した腕もないもないのに、バレてステージにあげられでもしたら大変だ。
私は、さながら超能力を隠す映画の主人公のように、何もわかりませんという顔につとめた。
最初のおじさんが弾いたあと、今度は台所で料理をしていた女将が出てきてじょんがら節を弾いてくれた。女将の語るような三味線は逸品で、目を閉じたまま完璧に繰り広げられる演奏に、私は素直に感動していた。女将から曲の合間に「どこから来たの?」と聞かれて「横浜です」などと返していたところ、恐れていた事態が起きてしまった。
「この子も弾くんですよ」
ババア。言いやがったな。
私は精一杯の表情で祖母に「言うな」という視線を送ったがもう遅かった。
顔を赤くして上機嫌の祖母は止まらない。長く習っているとか、団体で優勝しているとか、隠していたことをヘラヘラと発表してしまった。
さっきまで得意げだったおじさんはちょっと恥ずかしそうにしている。それを見た私も恥ずかしくなってニヤニヤしながらうつむいた。
そこからは予想通り「しばらく練習してない」だの「酔っぱらっているから無理」だのの言い訳と抵抗も空しく、最後は祖母のキラキラした期待のまなざしに負けて三味線を持たされた。
おじさんと女将と私。打ち合わせなしでなんとか合わせて弾いてみると、ほかのお客さんから歓声があがった。曲に合わせて手拍子と掛け声が飛んできて、私も楽しくなって「まあいっか」となって、一緒になってホーイホイと掛け声をかけた。
壁にぶつかって、思いつめて、三味線が嫌になって、遠ざかっていたはずなのに、こうして弾くとやっぱり楽しい。
祖母の嬉しそうな顔が見える。
10年前、決して安くない三味線を買ってくれたのは祖母だった。これで少しは恩返しになっただろうか。長い拍手の中、縮こまりながら席に戻った。
翌日。
この日は何軒か親戚の家を訪ねた。みんな80はとっくに超えていて、足が痛い腰が痛いと言っていたけれど、それでも畑をやったりして気丈に暮らしているようだった。
お土産に渡した鳩サブレが噛めるのかは怪しかった。キヌさんは「サチが来るといつも雨が降る」と言った。サチというのは祖母のことだが、祖母の名前はサチではない。
なぜサチと呼ばれているかと言うと、祖母の名づけに賛成しなかった曾祖父が、祖母のことを勝手にサチと呼び始めたかららしい。だから、津軽では祖母は「サチ」なのだ。ここでは祖母の本名を誰も知らない。
祖母は、ここにきて「サチ、サチ」と言われているうちに、私のことを「マキ」と呼ぶようになった。
マキは私の母の名前だ。
きっと、サチと呼ばれているうちに昔の祖母、つまり、私が生まれる前の祖母に戻ってしまったのだろう。
最初は祖父と一緒になって笑いながら訂正していたが、そのうちどうにも戻らなくなって、私はマキとして過ごすことになった。
津軽では私は「マキ」なのだ。
ここでは私の本名を誰も知らない。
また雨が降ってきて、祖母は「やっぱり私、雨女ね」と言った。
後半へ続く
<了>
ペンネーム:伊藤亜和(いとうあわ)
プロフィール:モデル・文筆家
おすすめ記事