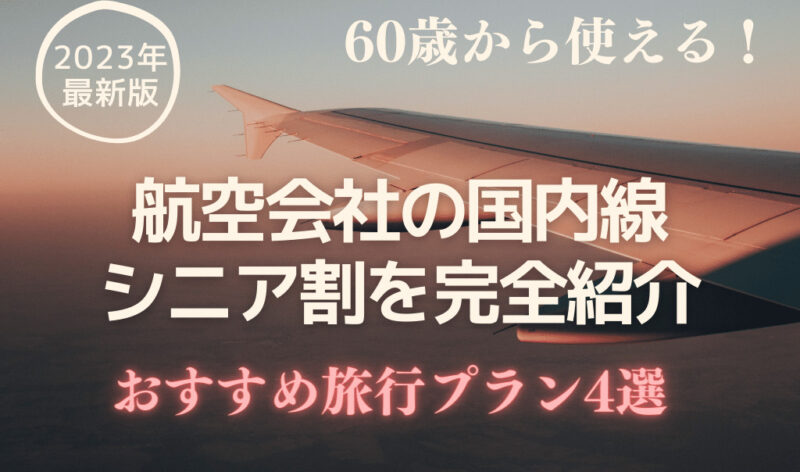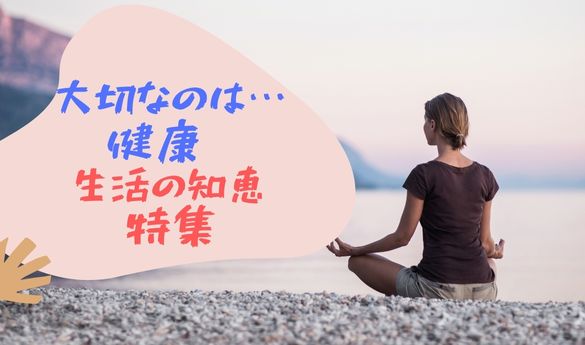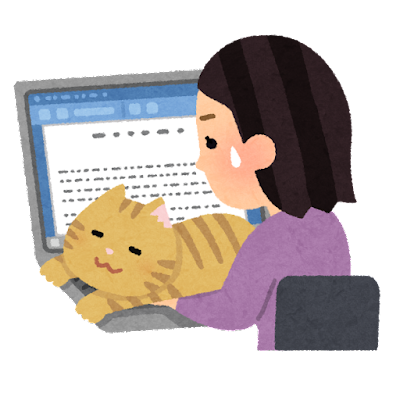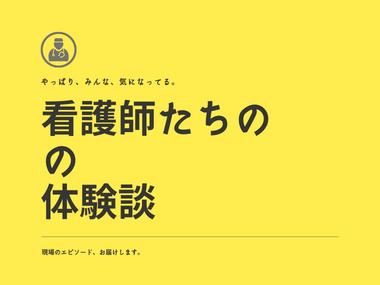高齢化に伴ってシニアという言葉がよく使われるようになりましたが、シニアとは何歳から呼ぶのかを知っていますか?
年を経て自分はシニアに該当するのかが気になっている人もいるでしょう。
この記事ではシニアとは何歳からなのかを詳しく説明します。
高齢者とシニアの違いも紹介するので参考にしてください。
日本では「シニア」が何歳からかは決まっていない

シニアは英語の「senior」をカタカナ語にしたものです。「senior」とは上級・上位・年上といった意味を持つ言葉で、高齢者を指すこともあります。
日本ではシニアが何歳からなのかは明確に定義されていないのが現状です。
ただ、高齢者の年齢については定義をしている機関があります。
国連・WHOによる定義
国際連合(United Nations)では高齢者(older persons)を60歳以上と定義していますが、国連の組織である世界保健機関(WHO)では高齢者を65歳以上という見解を示しています。
1956年の報告書で65歳以上の人口比率が高齢化率と定義された影響で65歳を境界線としているケースが多くなっています。
WHOでは65歳以上の人の中でも65歳~74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と定めて区別しているのが現状です。
厚生労働省・内閣府による高齢者の定義
厚生労働省ではWHOの見解に従って高齢者(elderly people)を65歳以上と定義しています。
内閣府による高齢社会白書でも高齢者は65歳以上とされているため、日本政府は高齢者を65歳以上と一般的には捉えていると言えるでしょう。
しかし、シニアと高齢者ではニュアンスに違いがあるので一概に65歳以上がシニアと断言できるわけではありません。
日本老年学会・日本老年医学会での定義
日本老年学会と日本老年医学会の高齢者に関する定義検討ワーキンググループでは、高齢者の定義と区分について以下のように提言をしています。
| 年齢 | 区分名称 |
| 65歳~74歳 | 准高齢者(pre-old) |
| 75歳~89歳 | 高齢者(old) |
| 89歳~ | 超高齢者(oldest-old, super-old) |
日本老年学会・日本老年医学会による見解に基づくと75歳以上でシニアになると考えることもできます。
しかし、「senior」が定義されているわけではありません。
シニアと高齢者の持つニュアンスの違い

このように高齢者の定義は存在しますが、シニアについては何歳からなのかを明確に定義している公的機関はありません。
シニア=高齢者とすれば65歳以上または75歳以上と考えられますが、なぜシニアに高齢者の定義をそのまま適用できないのでしょうか。
それはシニアと高齢者にはニュアンスに違いがあるからです。
ポジティブなイメージがある
特定非営利活動法人「老いの工学研究所」による2014年の「高齢者の呼び方に関する調査」ではシニアが呼称として最もポジティブに捉えられています。
高齢者・シニアのどちらもネガティブに捉えている人の割合が小さく、中性的な意味で用いられている点は共通です。
シニアは単純な年齢とは切り離されたポジティブな意味を持っているため、シニアは高齢者と同様に年齢で定義するのが難しいと言えます。
アクティブシニア・セカンドライフの意味合いが強い
シニアはしばしば「アクティブシニア」という活発に活動している高齢者をニュアンスとして含んでいます。
シニアライフはセカンドライフとも呼ばれ、定年退職後の生活をより充実させようという意味合いが強いのが特徴です。
シニアは高齢者ではあるものの、今後の生活に対してポジティブなニュアンスがあることがこのような関連キーワードからもわかります。
シルバーとシニアの違い。何歳からシルバー?
ではシニアとシルバーの違いはなんでしょうか?
日本の場合、シルバーは「高齢者」という意味に特定されている年齢層を指すことが多いです。
シルバーが「高齢者」を意味する由来を調べるとその発祥はシルバーシートと言う言葉になります。

シルバーは日本独特の言い回し
シルバーが高齢者を指すこととなった理由はシルバーシート部分の座席の色に銀色(シルバー)の生地を使っていたことが由来とされており、銀色から白髪のイメージが重なり、シルバー=高齢者というイメージが伝わり普及したものと考えられます。
そこから介護サービスに交付される「シルバーマーク」や高齢者向けの車を「シルバーカー」、高齢者向けの人材センターを「シルバー人材センター」、道路においても「シルバーゾーン」という区切りを設けている地区もあります。
シルバーは高齢者を指す
シニア同様に、シルバーは何歳からという厳密な定義はありませんが、シルバー向けのサービスが主に65歳以上の利用者が多く、高齢者向けのサービスをシルバー向けのサービスとと呼ぶことが多いためシルバー=65歳以上とみなされることが多いでしょう。また、高齢者を「シルバー世代」ということもあります。
では、シニアとシルバーの違いとなるとともに「高齢者」であることに変わりはありませんが、シニアはは先輩や年長者の意味合いもあり、若年者でもシニアという仕事上の役職があるなお幅広く活用されている一方でシルバーは日本独特の使い方となり「高齢者」のみを指すされる名称となっています。
シニアが何歳からかは変わっていく

日本の高齢者は厚生労働省によると65歳以上ですが、以前は60歳と言われていたこともありました。
定年退職の年齢は60歳が主流だったので、定年退職後からシニアライフが始まると考えるとシニアは60歳以上と考えることもできるでしょう。
つまりシニアが何歳からなのかは今後も変わっていく可能性があります。
高齢者や高年齢者の定義についても以下のように法律によって違いがあります。
| 法律 | 制定年 | 定義年齢 |
| 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 | 昭和46年 | 55歳 |
| 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 平成13年 | 60歳 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律 | 昭和57年 | 65歳以上(前期高齢者)・75歳以上(後期高齢者) |
シニアが何歳からかは時代と共に変わるので、大まかに高齢者と同じ65歳以上という認識をするのがいいでしょう。
シニア割引などを利用するときには定義を調べて、該当するかどうかを確認しましょう。
また、キラキラシニアタイムスではシニア割引やJR等の交通機関がお得に利用できるサービスもまとめていますので参考にしてください。
まとめ

シニアが何歳からなのかは明確な定義がなく、もし定義されたとしても時代と共に変わっていきます。
厚生労働省でもWHOでも高齢者は65歳以上と定義しているので、シニアの年齢的な目安にはできるでしょう。
しかし、シニアにはポジティブでアクティブな意味合いが込められています。
年齢を問わずにセカンドライフを始める段階でシニアに仲間入りしたと考えることもできますので、年齢にこだわらずにポジティブなシニアライフを築き上げていきましょう。
<了>
・シニア割引きで豊かな老後生活!
・おすすめ老人ホーム東京編