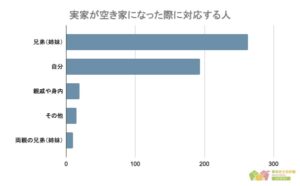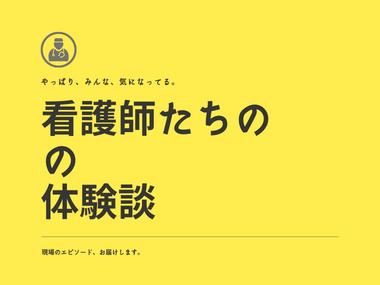独特の感性と芸術性の高い文章力によりSNS等で話題の文筆家「伊藤亜和さん」によるオリジナルコラムです。
同居されている祖父母様との日常を甘辛な文章で紡いでいきます。
今回は「サチの里帰り 後編」です。
それではどうぞ。
前回のお話はこちら
山男とじょっぱり女、ときどき、あやしい孫 ⑤

広い畑が見渡す限り遠くまで続いていて、日は間もなく沈もうとしている。
雨を降らせたり、引っ込ませたりしている大きな雨雲が、分厚い天蓋のように地上にのしかからんと迫っていた。
車でいくつかの無人駅を通り過ぎる。
やはり誰もいない。
ミツオおじさんの家を訪ねたとき、家系図を見せてもらった。畑の相続のことでもめているらしく、わざわざ調べてもらったらしい。ミツオおじさんは7人兄弟の末っ子で、兄弟のいちばん上の長女にはヨシと名前があった。ヨシは私の曾祖母で、私が小学生のころまで生きていた。月に何度か、曾祖母を訪ねて老人ホームに行っていたことを思い出す。私は曾祖母のことを「ばあちゃん」と呼んでいた。訛りがとてもキツい人で、私はほとんどばあちゃんの言っていることを理解できなかった。それでもばあちゃんは私をかわいがって絶え間なく話しかけてくるものだから、私は笑顔でうん、うんと曖昧に返事をして、分からないなりにせめてもの孝行をしようと、一生懸命ばあちゃんの入れ歯を洗った。
祖母の強情な性格はばあちゃん譲りのものだと思う。介護士さんにやってもらえばいいものを、無理にベッドの手すりによじ登って棚の上のものを取ろうとして、案の定足を滑らせ骨折したこともあった。あのとき、祖母はばあちゃんを叱りつけていたけど、祖母がもっと歳を取ったら、きっと同じようなことをしでかすにちがいない。家系図を見た私は、ヨシばあちゃんとミツオおじさんに挟まれた兄弟たちの内、3人の享年が5才にも満たないことを知り、その切なさで目を細めた。昔は病院なんてなくて、簡単に死んでたんだよ、とミツオおじさんは言う。もし、ばあちゃんが同じように早くに死んでいたとしたら、祖母は生まれず、そして私も生まれなかった。私が帰るときにはいつも「また来いよぉ」って言ってくれてたっけ。それだけは分かっていた。
あの日、火葬したばあちゃんの身体から、骨に交じってたくさんのボルトが出てきたのを見た。生き抜いてくれてありがとうと、今になって思う。
曾祖母は88で亡くなった。祖母は今年88になる。車いす生活だった曾祖母に比べたら、いまだに元気に階段を上り降りして家事をこなす祖母が、まもなく死んでしまうとはとても想像できない。この人はまだ死なないのだろうけど、いつかその時は必ずやってくる。私も、私の母も、祖母に甘えすぎている。私たちは、祖母がいなければ唐揚げも揚げられないし、だし巻き卵もろくに作れない。祖母から生活のアレコレを教わるどころか、祖母がどんなふうに生きてきたかさえ、ろくに知らない。祖母は青森に向かう途中、私に「私がどこで生きてきたか教えてやる」と言っていた。今回、私を一緒に連れてきたのはそのためなのだろう。祖母がどこで生まれ、何を思って生きてきたのか、口下手な母に代わって、それよりいくらかはマシな私が聞いておかなければならない。
車を運転しながら、助手席の祖母に「青森のどこで生まれたの」と聞いてみる。テレビで青森の映像が流れると、祖母はたいてい「ここにいた」「ここにもいた」と言っているので、実際出生の場所がどこなのか、私はいまいち分かっていなかった。
祖母は「わからない」と言った。
続けて「本籍が、なかったから」と言った。
本籍がない。つまり、戸籍がなかった。
生まれたときに出生届が出されていなかったらしい。
どこかの山奥で生まれた祖母は、小学校にもろくに通わせてもらえないまま奉公に出された。横浜に来て結婚するまで、自分に戸籍がないことを知らなかった、と語った。
役所に人が手続きをしてくれて、最終的に祖母の父が生まれた秋田に戸籍を作ってもらったそうだ。
だから、彼女がどこで生まれたのか、今となっては誰も知らず、彼女自身も知らないという。
「たぶん、この辺りだと思うんだけどねぇ」
目の前の畑を眺めながら祖母が言った。自分はここで生まれたのだと、しっかりとその場所に旗を立てることができないというのは、いったいどんな気分なのだろう。近頃、自分の遺骨を海に巻いたり、宇宙に向かって飛ばしたりしたい、という話をよく聞くけれど、私はその行為に全く憧れることができない。自分の墓もなく、水や風に乗ってだだっ広いどこかに葬られることを想像してみると、拠り所もなく、言いようのない不安に包まれる。祖母は生きながらにしてそうなのだろうか。祖母の存在が、突然ふわりと宙に浮いて漂っているように感じた。
祖母にとっては、この青森の大地そのものが故郷で、はっきりと示された「点」ではなく、布ににじんだインクのように、じんわりとぼやけた思い出が広がっているのかもしれない。本人がそれをどう感じているかは分からない。だけれど、今の祖母には私たち家族がいる。綿毛のように飛んでいた彼女が土に根を張って、私たちを作ったのだ。私は良い孫ではないかもしれないけど、今、ここまで生きて、言葉を交わして、祖母の隣にいる。それだけでも彼女のなかにあったかもしれない孤独を癒すことができていたのなら、生まれてきてよかった、と思えるような気がする。
3日目になって、日本海はようやく晴れた。浅虫のほうへ海沿いをずっと走って、野辺地のホテルへと向かった。つぶれてボロボロになった旅館の廃墟があちこちに取り残されている。東京や横浜ではこういう光景はあまり見ない。都会では潰れたらすぐ更地になるか、すかさず居抜きが入るかのどちらかだ。代謝も改革もこの町にはなく、そのままの時の流れと、人の死によって、静かに淡々と動いていた。都会という不自然に、毎日身をさらして生きている私は、またこの光景を「寂しい」と書いてしまいそうになる。違う、これこそ自然なのだ。始まりも終わりも、決して突然ではなく、広い水面のどこかで浮き上がるあぶくのような、いつ生まれたのかも、弾けたのかも分からない。
ただ、目の前のすべきことだけを全うする一生が、ここにはあるのかもしれない。
祖母の出生地に続いて、長い間気になっていたことを聞いてみた。私の叔父にあたる人物のことだ。
「叔父さんはさ、なんで死んじゃったの」
「高いところかあら落ちたんだよ」
「どうして落ちちゃったの」
「会社に勤めはじめて、飲んできた日に、会社の事務所で寝ようとしてたんだと思うよ。事務所のカギが見つからなくて、それで酔ってるもんだから、建物の壁についてるパイプをよじ登って窓から入ろうとしたんだろうな。それで、落っこちて死んじゃった。私が持たせた弁当箱しょったまま、死んでたよ」
「そっか」
面倒見がいい人で、まだ小さかった妹、つまり私の母を、初任給でディズニーランドに連れていくと約束していたらしい。それも果たせず死んでしまったから、私は当然、叔父さんをリビングに飾ってある写真の中でしか知らない。まだ元気なもう一人の叔父さんと顔がそっくりだ。このふたりの叔父さんと、その下の叔母さんの父親は北朝鮮人だったらしく、私の祖父ではない。運命が変われば私の祖父にもなるかもしれなかった人物の顔は、この3人の顔を見ればなんとなく想像がつく。
もう一人の叔父さんは毎年大みそかに家に来ると、酔っぱらって母と私を膝の上にのせてかわいいかわいいと言う。母はもう50にもなるというのに、その時だけは妹の顔になっていた。その叔父さんももし生きていたら、かわいがりたがりの酒臭い叔父さんがふたりいることになっていたのだろう。私は、会ったことのない叔父さんに寂しいという気持ちは湧かないけれど、隣に座る祖母は少しうつむいて「今でも思い出すよ」と静かに言った。
私たちの車はそれほど広くない墓地にたどり着いた。ここにも他に人はいなくて、管理人の姿もなく、仏像や人形が保管された小屋の中には無造作に線香が放ってあった。小銭を供えて数本拝借し、祖母は私を「小山内」と書かれた墓地の前へ連れて行った。
「ばあちゃんー、来たよー。サチだよー。」
祖母はそう言いながら嬉しそうに墓に水をかけ、まんじゅうを供えた。祖父と後ろでそれを見守りながら、私は祖父に「これは誰の墓なの」と尋ねた。
「これは、ヨシさんのお母さんの墓」
曾祖母のそのまた母、ということは祖母の祖母のお墓らしい。一瞬納得しかけたが、情報がうまく一致しない。
「ヨシばあちゃんの名字って斎藤じゃなかったっけ」
「そうだな」
「しかも、タチの旧姓って高橋じゃなかった?どういうこと」
「…さぁ」
祖父は曖昧に答えてヘラヘラと笑う。もう、訳が分からない。私はそれ以上深く聞くことをやめた。にじんだインクの模様でできた形を、そのまま曖昧に眺めることにした。すべてを知る必要はないのかもしれない。小山内の墓の正面には、雲一つない青の中、堂々と津軽富士がそびえている。とにかく、私が今ここにいることが奇跡であると、思い知らされたようだった。「自分を大切に」なんて、気恥ずかしくて笑ってしまうけど、こうしてでたらめにも繋がってきた命はしっかりと受け止めなければならないと思う。
祖母は墓に手を合わせて「まだ、そっちは行かないからね」と呟いた。
車に戻って頭を触ると、髪のなかにはひんやりと冷たい津軽の風が留まっていた。
せば、帰ろっか。
<了>
ペンネーム:伊藤亜和(いとうあわ)
プロフィール:モデル・文筆家
おすすめ記事